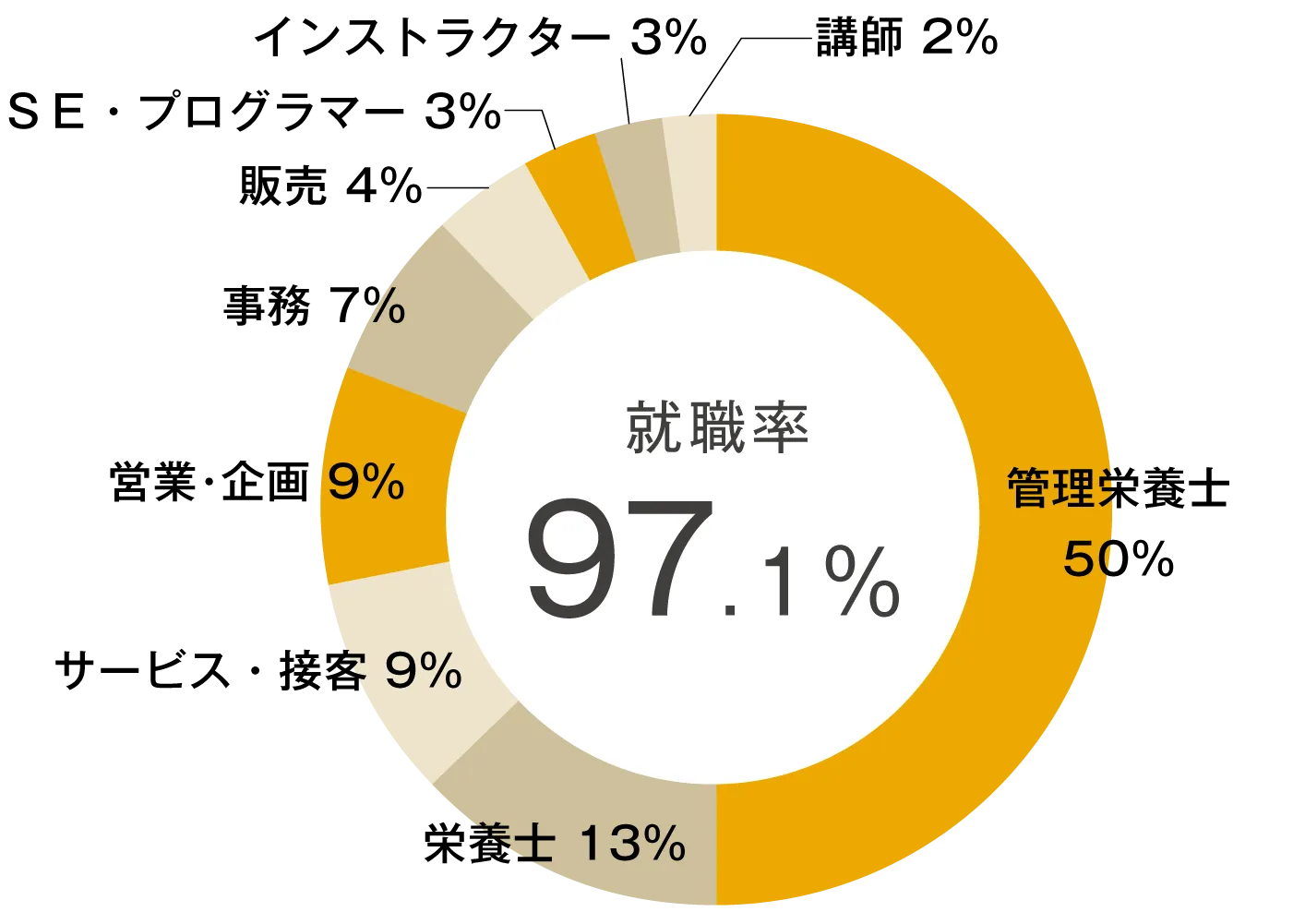生活科学部 食生活科学科 管理栄養士専攻 2025年4年卒業
(2026年4月より食科学部管理栄養学科)
(長野県 上田染谷丘高等学校出身)
※インタビュー内容・情報は取材時のものです
Q1この学科で学ぼうと思ったきっかけはなんですか?
管理栄養士を目指し
落ち着いた学びの環境へ
もともと食に関心があったことと、高校時代のインターンシップで、離乳食について母親の相談に乗る管理栄養士の親身に寄り添う姿勢を目の当たりにしたことで、管理栄養士を目指すようになりました。児童生徒への食育に関わる栄養教諭の資格が取得できることと、日野の落ち着いた環境で学べることも魅力だと思い志望しました。
Q2特に印象に残っている授業はなんですか?
座学から現場の応用へ
現場の状況や効率を想定し課題解決を
「解剖生理学a」,「臨床栄養管理実習」です。糖尿病や脂質異常症などの疾患に応じた治療食の内容や栄養管理などの応用を学びました。病院では限られた時間、人員で大量調理を行い、授業で扱う疾患数に比べ多くの種類の治療食を作るので栄養管理はもとより正確性や効率が共に重要です。調理実習では自分たちの献立を実際に作ることで多くの気づきがあり、これが後の臨床栄養学実習(病院実習)で、栄養価計算の数字だけでなく、現場の実情を考慮して献立を作成する必要性とつながり、さまざまな可能性を想定して課題解決方法を考える経験となりました。

Q3各年次での学びを通じ、どんな感想を持ちましたか?
見えて来た行政管理栄養士への道
地域に寄り添い、疾患予防などに関わっていきたい
1年次に栄養に関する基礎知識を一から学び、難しく大変でしたが頑張って学んできてよかったと思います。2年次の学内実習や実験の伴う学習は、3年次の学外実習の足がかりとなりました。3年次では病院、保健所、給食施設での学外実習を経験するとともに、各施設によって分野の異なる管理栄養士の役割も学びます。その中で地域住民により近い支援を行える行政管理栄養士を目指して、疾患の予防から関わりたいと思うようになりました。これから就職活動も始まりますが、ゼミでの研究や卒論、国家試験対策などにも力を入れ学生生活の集大成にしたいと思います。
Q4将来への希望と、本学での学びから社会に出た後役立つと思う考え方やスキルはありますか?
人と向き合う管理栄養士には
協調性と洞察力が必要
管理栄養士は人と向きあう職業なので、周囲と協力する協調性が重要だと思います。自分と異なる意見に最初は納得できなくても、理由がわかり理解することで受け入れられることもあり、まずは聞くことが大切だと思いました。期限のある課題をグループで完成させるために、各自の分担制にしますが、皆忙しいので、予定通り進まないこともあります。全体を見回し、自分からも率先して声かけして調整した経験は将来役に立つと思います。また、座学や実習で培った多面的な視点で解決策を考える洞察力は今後も大いに役に立つと思います。
Q5これから実践女子大学を目指す高校生たちへのメッセージをお願いします。
積極的なコミュニケーションで
知識や視野を広げよう!
グループワークが多いので、自分の役割を認識して、積極的にコミュニケーションを取ることで視野が広がりより高い知識を得られると思います。食生活科学科は理系科目が多いですが、先生も熱心で丁寧に教えてくださるので、食や栄養に関心がある人は文系でも基礎からしっかり学ぶことができます。サークル活動や常磐祭にも参加でき、キャンパスライフも楽しめます。